

契約書は紛争予防・紛争回避のために作成されるべきものです。しかし、実際のところは、契約締結の際に「紛争予防・紛争回避」の観点から十分なチェックをしている人は少ないのが現状です。
チェックする重要箇所は多岐に渡り、事案ごとに盛り込むべき条項等も変化するため、まずは専門家に依頼する事をお勧めしますが、ここではその中から2つの事項についてご説明いたします。
法律用語は正確に使用されているか
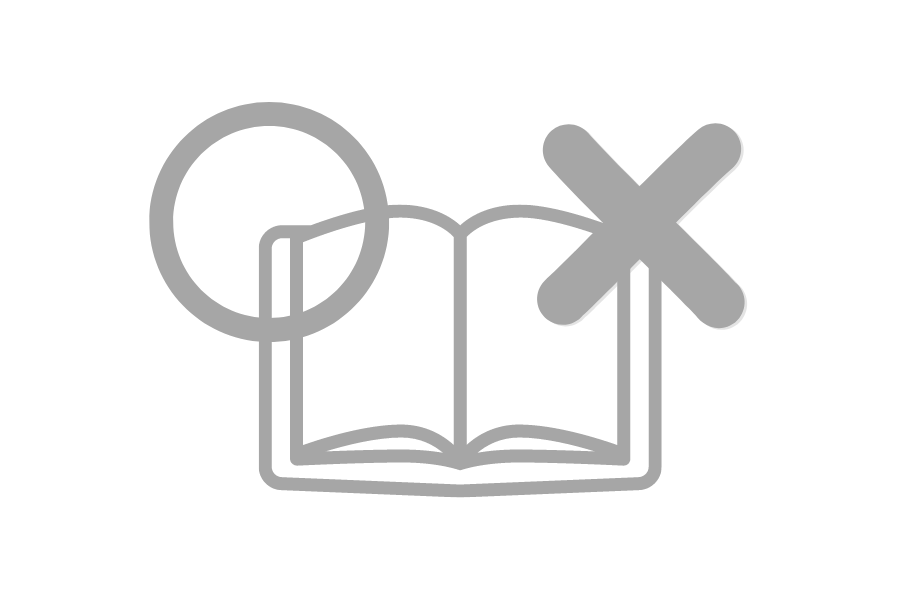
契約書の中で使用する法律用語は正確に使用しなければなりません。法律用語は不正確だと、条文の意味が全く異なってしまうおそれがあります。その結果、せっかく契約を作成したにも関わらず、不正確な法律用語を使用したせいで、将来の紛争の原因となる可能性が残ってしまうのです。
法律用語が正確に使用されていない例文
この条文でいう「破産宣告」と言う言葉は改正前の破産法の用語で、現行破産法では「破産手続開始決定」という用語に変更となっています。この条文のままだと「旧破産法の破産宣告があった場合には解除可能」と言う解釈、つまり「現破産法の破産手続開始決定があった場合には解除できない」と言う解釈が成立してしまいます。このままだと将来の紛争の原因となってしまいます。
法律用語
例えば、上記の「破産宣告」だけでなく、「会社整理」については、旧商法の用語であり、会社法制定時に廃止されていたり、「禁治産宣告」と言う用語は民法改正により廃止されていたり、最近の民法改正では「瑕疵担保責任」が廃止され新たに「契約不適合責任」となっております。内容に関しても瑕疵担保責任とはいくつか変わっている点もありますので、注意が必要です。他にも最近の民法大改正で「消滅時効」「法定利息」「債務不履行解除」「保証」の内容も変更しているので注意が必要です。
法律用語の難しさ
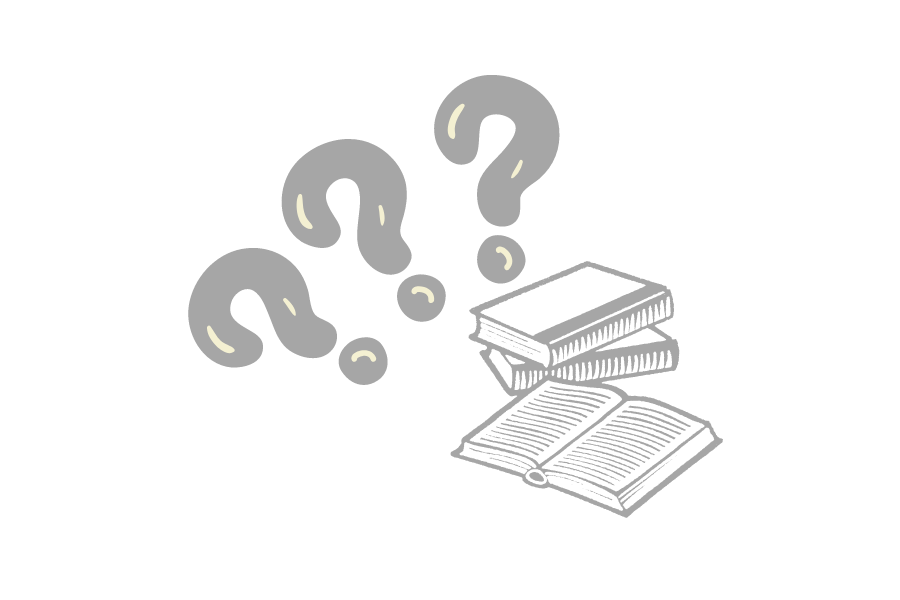
法律用語は正確に使用しなくてはいけません。不正確な法律用語を使用することは、日常用語と曖昧に使用する場合よりも、はるかに紛争のリスクが高まります。特に日常用語と類似した法律用語を気軽に使用すると大変な結末に発展する危険性もあります。法律用語は、それによって法律的な効果を生じさせる場合が多いので慎重な取り扱いが必要です

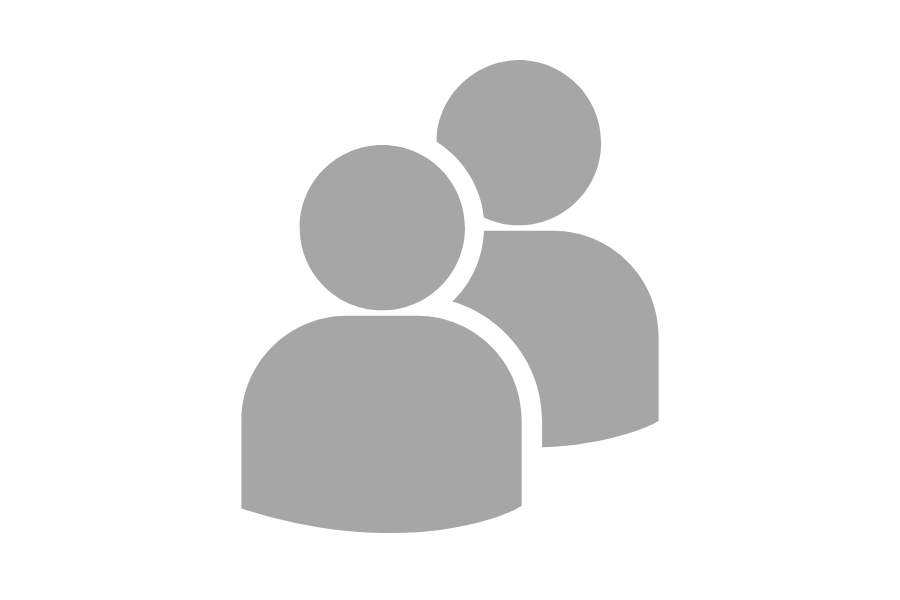
契約書において、契約書の当事者となる人の名前(名称)は正しく明記されてますでしょうか?契約の効力は、契約当事者に及びます。契約した当事者がその効力に拘束されるのです。逆に契約当事者ではない人には効力は及ばないという事になります。
契約当事者を正確に表示する必要性
契約当事者が正しく表示されていないと、本来契約当事者であるべき者に契約の効力が及ばなくなる可能性があります。紛争予防のためにも、まず、契約当事者が正確に書かれているかチェックしてみましょう。
当事者名の簡略化
当事者名が長い場合、普段より簡略化した名称で活動していて、ついつい簡略化した名称で契約書の当事者名称を表示してしまわないように注意しましょう。例えば、正式名称が「ジャパンアーティスト・クリエイティブマネジメント株式会社」であるのに契約書の当事者名称に「ジャパン・マネジメント株式会社」と表示してしまうと、本来契約する予定の当事者(ジャパンアーティスト・クリエイティブマネジメント株式会社)とは全く異なる名称の別会社(ジャパン・マネジメント株式会社)との間で契約が成立したように読むことができてしまいます。これだと後々の紛争の原因を内包することになりかねません。
屋号で表示している(個人事業主)
個人事業主やフリーランスの方で契約を結ぶときに注意が必要なのが「屋号だけで表示」してしまうパターンです。屋号単体では契約当事者として特定できていない事になってしまいます。屋号は、会社や法人のように第三者が公に確認できるような登記がされていない場合、当事者と特定している事にはなりません(屋号の登記制度自体はあります)
表示する際は「〇〇(屋号)こと〇〇(代表者氏名)」と表示するようにしましょう。
法人か個人かわからない
例えば「株式会社山田太郎」が契約の当事者だった場合を考えてみましょう。実際の契約書には「山田太郎」としか表示されていなかった場合、「株式会社」を省略して表示してしまうと、文面を外形的に見る限り、契約は「個人」である「山田太郎」との間で成立するものと解釈できてしまいます。
このように安易に株式会社を省略してしまうと、契約書を取り交わしたにも関わらず、契約当事者が誰なのか?という根本的な疑問が生じてしまい後々の紛争の原因になってしまう為、注意しましょう。
以上の事から契約書に記載する当事者の名称は「契約の効力が誰に及ぶのか」という点でとても大切になります。後々の紛争を回避するためにも当事者を特定できるよう明確に表示するように気をつけていきましょう。




